全飲連ニュース紙上セミナー 近畿ブロック講習会 平成19年9月12日 |
|
「原産地表示」と「食事バランスガイド」の普及促進 |
|
激動の飲食業界にあって 個店の進む道を考える |
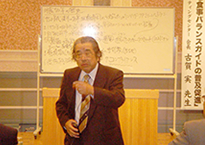 |
| ■講師 株式会社日本コンサルティングセンター 代表取締役 古賀 実 氏 |
|
●まず時代の流れを的確につかむことが大切
外食産業の市場規模は24兆円。百貨店とスーパーの販売合計を上回る巨大産業が時代の節目を迎えています。特に、かつて一世を風靡したファミリーレストランが、衰退傾向をたどっており、日本フードサービス協会の調査によると、2006年の顧客数は2%減。10年連続しての減少となっています。
すかいらーくが登場した1970年以降、ファミレスはいきなり近代的な事業モデルを取り入れ、まさしく日本を代表する産業の主役を張ってきました。これを支えてきたのは、団塊の世代、洋食に不慣れなサラリーマンは、フォークやナイフの使い方を、ファミレスで覚えたと言っても過言ではありません。週末には家族でファミレスに行くのがささやかな楽しみとなりました。しかし、団塊の世代のリタイアが秒読みになり、少子高齢化が深刻化してきました。そして食の安全を脅かす様々な事件が発生し、消費者の食への不安や意識が高まっていることや、メタボリック症候群などへの関心から食事バランスにこだわる人々が増えているなど、外食産業を取り巻く環境は大きく変化しました。
こうした激動の中にあって、知恵とこだわりで独自の道を切り開いている店舗の事例を見てみましょう。
●低価格の時代の中の工夫
▽「ダイヤモンドダイニング」という外食チェーンがあります。お客様の感動や歓喜につながるようなコンセプト・空間・ストーリー(物語)の3つを、内装・サービス・料理など至るところに織り交ぜ、常にワクワク・ドキドキするような斬新な店づくりに挑戦しています。41店舗を所有していますが、それぞれの店舗にはそれぞれ個性があり、メニューも制服も全て各店舗に大幅な権限委譲を行っています。全店共通の食材が80%で、あとの20%は各店の自由。それにより店舗ごとに状況に合わせてた対応が可能となり、常に革新的なメニューづくりができるうえ、食材・飲材の廃棄率を抑えることができます。
▽「カレーハウスCoCo壱番屋」は、カレーの辛さと量が選べ、トッピングも様々。オーダーごとに一つ一つ鍋で温めて出すことにこだわっている。また、店舗を持ちたいという社員には、最短2年、最長5年間フランチャイズの勉強をする機会を与える他、修行以外にも独立資金づくりも計画的に行えるようバックアップするといったおもいやりのフランチャイズを展開しています。
▽ある和食レストランチェーンの平均客単価は4,400円。昼は2,500円で、夜は6,000円~7,000円。だいたい4人で来るので1組約3万円の売り上げです。1店舗当たりの従業員数は平均8人。一人は店長、一人はホール担当で、残りは全員調理師。この調理師を代議士を撮るプロのカメラマンに撮らせて、写真を額縁に入れて店に飾っておく。するとお客さんは、6,000円を高く感じなくなってしまいます。本当にちょっとした見せ方、アイデアです。
●良質な素材と美味しさ、上手にアピール
良い素材を使っておいしく、安価にお客様に食べていただく。そして原価率を下げるよう工夫と努力をします。コンプライアンス(法令を守る)として、原産地表示をしっかり行い、「特別に選びました。間違いありませんのでご安心ください」というメッセージをお客様に伝えます。高かったら、なぜ高いのかを説明することが大事。単品とセットメニューの料金格差を明記する。2人、3人、4人で行って食べても同じ料金ですか? お客様に何らかの還元があってもいいですね。
メニューには生活習慣病予防やメタボリックシンドローム対策としてカロリー計算を入れましょう。商品、価格、メニューは個性なので、しっかり明記して伝えるべきです。ロイヤルホストや藍屋は国産食材を使用していることをネットなどでもアピールしていますが、大手は宣伝上手です。個店でも宣伝上手になれるようバックアップするのは、全飲連の使命です。
●M&Aの時代に突入
これからは、欧米諸国だけでなく中国にも我が国の企業が買収されるようになるでしょう。時代は大きくうねっています。自分も変わらなければ生き残れません。それも革命的にです。阿倍さんのような坊ちゃんではダメです。88歳の岸信介氏と一緒にゴルフをしたことがあります。杖をついておられて、9ホールで止めようと言っていたのに、中国大使が一緒に回るとなったら、心意気で回りました。こういう精神力こそ見習いたい。
外食の歴史は1950年代からはじまりました。約70年前後に回転寿司が流行り、70~80年代は持ち帰り弁当チェーンができました。共稼ぎが増え消費スタイルが変化。週末はファミレスが盛る。また、日本一の本屋はセブンイレブン。夜中に本を買うのだ。牛乳屋や酒屋はスーパーに喰われてしまった。家電小売店はほとんど無くなり「ヤマダ」や「コジマ」などによる小型店買収の占有率が高くなりました。
飲食業にも同じことが言えます。すかいらーくの4兄弟も他社に販売権を売りました。流通業でも、セブンイレブン・イトーヨーカドーを中心としたセブン&アイ・ホールディングスが、西武・そごうを経営統合しました。
こうした大きな資本が動く、大きなうねりの狭間で、我々個店は身を削って命がけでお客様においしいものを提供しているのです。理性とプライドをもってのぞめば、未来は明るいはずです。
●ピンチはチャンス! 新たな道を自ら切り開く
大型飲食チェーンで有名な「ワタミ」は、介護業界にも参入していますが、自らの農場で栽培した有機野菜や、北海道の自社牧場で生産した牛肉などを、飲食店と介護施設に取り入れ、安心安全な食材として利用しています。渡邊美樹社長に、「これからレストランをするの?」と聞いたところ、農業をやるということでした。学校給食や老人ホーム、スーパー、レストランなどへも良質な食材を提供していきたいということです。飲食業で培ったノウハウがしっかり土台として築かれているのです。
また、道路交通法の改正などを背景に、来店客が落ち込んだことを受けてタクシー会社と提携して、お客様のタクシー利用代金を一部ワタミが負担するというサービスにも取り組んでいます。例えば、食事代が1万円以上なら2,000円ワタミが負担。1万五千円以上~2万円以下は3,000円。2万5千円以上から5,000円アップごとにプラス500円。このようなサービスは、飲酒問題で2割減となった客足を取り戻そうという試みとして、他のタクシー会社と飲食店との間でも行われていますが、アゲンストの風をどうするかと、知恵を絞った結果です。
さらに、店の売り上げを上げようと思ったら、客単価を上げることを考えるべきです。高単価のものを作って売る努力をするのです。うどんやラーメンといった単品は難しいです。トッピングや小皿を多用したり、プラスをお客様に還元したりする方法を考える。また、葬式、お祝い、同窓会、会合などの宴会を徹底してとる。一度利用していただいたお客様に、またのご利用をお願いします等の声かけを徹底して行います。こういうことをコツコツやっているところは伸びていきます。
●一流の後継者を育て、繁栄し続ける
ある日、東海大学の近くの子どもが輸血が必要になたため、柔道の山下さんのところに、輸血をしてくれる人を紹介してほしいという依頼があった。部員の中で普段柔道が弱い男が、輸血をすることを志願した。その男の子どもを可愛がる様子がなんとも温かく、それを見ていた山下さんは、〝自分も血液型が一致していたのに、自分が行くべきだった〟どこかに世界の山下という自惚れがあったことを自覚した。山下さんは、その男を誉めると、どうしたことか、その男の柔道がめきめき強くなっていった。
つまり、個店はそういうものだと思うのです。後継者の面倒を見て、一流に育てて後を譲っていく。謙虚に学ぼうとする姿勢が、個店である皆様方の店をよく育てていくだろうと思います。
以上、少しでも皆さんのご商売のヒントとなれば幸いです。ありがとうございました。
(紙面の都合により講演要旨を掲載いたしました)
●プロフィール
1931年11月15日、福岡県生まれ。早稲田大学卒業後、企業実務を経て、1960年コンサルタント業務に投じる。1966年、株式会社日本コンサルティングセンターを設立。いわゆる民間のコンサルタントを産業界に定着させた功労者。新入社員教育や幹部社員教育のカリスマ講師であり、中小企業から上場した会社も多く手がけている辣腕コンサルタント。著書は『人の採用が出来なければ会社は潰れるーー人手不足解消の決め手はこれだ』(マネジメント社)『二世経営者の帝王学--キミは親を超えるために生まれてきた』(現代書林)など多数。