厚生労働省、農林水産省
フードガイドの名称とイラストを決定
食生活指針を具体的な行動に結び付けるものとして、食事の望ましい組合せや、おおよその量をわかりやすくイラストで示したものがフードガイド(仮称)です。厚生労働省と農林水産省は、昨年12月から共同で、「フードガイド(仮称)検討会」(座長;吉池信男・独立行政法人国立健康栄養研究所研究企画評価主幹)を設置し検討を進めてきました。全飲連からも田中清三会長が委員として参加し、多くの提言を行なってきました。
今回、決定・発表されたフードガイドの名称及びイラストは以下のとおりです。
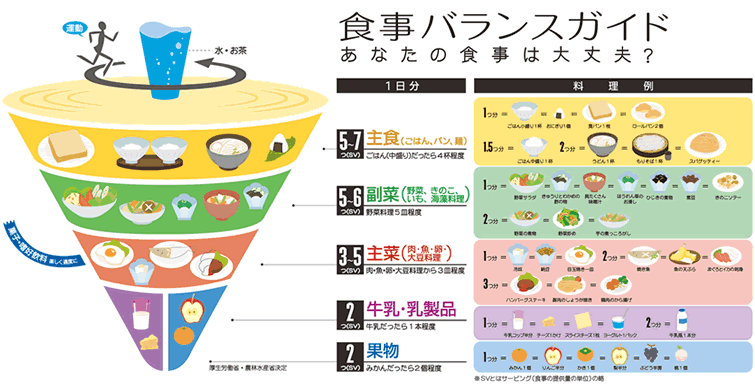 |
■名称は「食事バランスガイド」
「何を」「どれだけ」食べたら良いかを一般の生活者にわかりやすく、イラストで示したものについては、世界的には「フードガイド」と呼ばれることが多いようです。従って、その言葉を中心としながら、今回は、回転(運動)することにより初めてバランスが確保される〝コマ〟の型を採用したことも踏まえて、名称に「バランス」という言葉を入れました。また、食品単品の組み合わせではなく、料理の組合せを中心に表現することを基本としたことから、「フード」ではなく、個々人の食べるという行為も意味する「食事」という言葉を用いることとしました。
■イラストについて
見る人にとって最も目につく上部より、十分な摂取が望まれる主食、副菜、主菜の順に並べ、果物と牛乳・乳製品については、同程度と考え、並列に表現しました。形状は、日本で古くから親しまれている「コマ」をイメージして描き、食事のバランスが悪くなると倒れてしまうということを表しています。また、コマが回転することは、運動することを連想させるということで、回転(運動)しないと安定しないということも、合わせて表すこととしました。
また、菓子・嗜好飲料・食事の量の中でバランスを考えて適度にとる必要があること、一方で、食生活の中で楽しみとしてとられている現状があり、食事全体の中で量的なバランスを考えて適度に摂取する必要があることから、コマを回すためのヒモとして表現し、「楽しく適度に」というメッセージを付すこととしました。
■今後の普及について
国民に広く親しみやすくかつ身近に活用できるよう、ポスター、パンフレットなどを作成し、以下のような普及活用を図るとともに、とりわけ生活習慣病予防の観点から、男性肥満者、単身者、子育て世代といった対象に焦点を絞った普及活用(肥満、エネルギー及び脂質の摂りすぎ、野菜不足、朝食欠食などの解消への取組)に配慮することとしている。
(1) ファミリーレストランなどの飲食店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の食品産業における活用を通じた普及活用
(2) 地域(健康づくり教室など)や職場を通じた普及活用