暯惉16擭搙惗塹怳嫽悇恑帠嬈丒挷嵏尋媶曬崘儗億乕僩
暘墝懳嶔悇恑偺偨傔偵杒嬨廈巗偺庢傝慻傒傪帇嶡
| 丂慡堸楢偱偼丄暯惉16擭搙傕暯惉15擭搙偵堷偒懕偒乽惗塹怳嫽悇恑帠嬈乿偲偟偰丄暘墝懳嶔悇恑帠嬈偵庢傝慻傒傑偟偨丅
|
暘墝懳嶔悇恑儌僨儖抧堟帇嶡媦傃尰抧堄尒岎姺夛嶲壛幰柤曤(弴晄摨丒宧徧棯)
仠慡堸楢娭學
揷拞惔嶰夛挿乮戝嶃晎棟帠挿乯丄壛摗棽憤柋埾堳挿乮孮攏導棟帠挿乯丄拞搰峃夘嵿柋埾堳挿乮廐揷導棟帠挿乯丄桍愳堦楴暉巸岤惗埾堳挿乮恄撧愳導棟帠挿乯丄怷愳恑帠嬈埾堳挿乮惷壀導棟帠挿乯丄愇愳搶岟慻怐奼廩懳嶔埾堳挿乮嶉嬍導棟帠挿乯丄幊摴災堦榊戝夛埾堳挿乮捁庢導棟帠挿乯丄悪惓摴暉壀導棟帠挿丄抾壓榓惗孎杮導棟帠挿丄彫忛揘榊愱柋棟帠丄彫抮弐峎帠柋嬊師挿丄悰揷柧懃慡堸楢僯儏乕僗曇廤挿
仠杒嬨廈巗曐寬暉巸嬊娭學
烴杮傦傝巕曐寬堛椕晹寬峃悇恑壽庡嵏丄帥惣懽巌曐寬堛椕晹寬峃悇恑壽抧堟曐寬學乮廱堛巘乯丄彫惣帯巕曐寬堛椕晹寬峃悇恑壽庡嵏乮娗棟塰梴巑乯
 |
杒嬨廈巗偺庴摦媔墝杊巭懳嶔偺庢傝慻傒忬嫷 杒嬨廈巗曐寬堛椕晹寬峃悇恑壽庡嵏丂烴杮傦傝巕偝傫偵暦偔 |
丂杒嬨廈巗偼丄儖僱僢僒儞僗峔憐偺傕偲偵乽悈曈偲椢偺傆傟偁偄偺崙嵺僥僋僲儘僕乕搒巗乿傪栚巜偟偰偍傝丄媔墝懳嶔傕偦偺庢傝慻傒偺堦偮偱偡丅
丂暯惉16擭搙偺庴摦媔墝杊巭偵娭偡傞庢傝慻傒偼丄嘆庴摦媔墝杊巭懳嶔尋廋夛丄嘇嬛墝嫵幒丄嘊島墘夛丄嘋尋廋夛摍偱偺島墘丒島榖丄嘍屄暿嬛墝僒億乕僩丄嘐堸怘揦嬛墝丒暘墝幚懺挷嵏寢壥丄嘑巤愝撪嬛墝丒暘墝嫤椡億僗僞乕丄僠儔僔嶌惢攝晍丄嘒峀曬妶摦偺俉偮偺僇僥僑儕乕偵暘偐傟偰偄傑偡丅
丂崱夞偼堸怘揦偵摿偵娭學偺怺偄庢傝慻傒偱偁傞丄嘆庴摦媔墝杊巭懳嶔尋廋夛丄嘑巤愝撪嬛墝丒暘墝嫤椡億僗僞乕丄僠儔僔嶌惢攝晍丄偦偟偰丄嘐堸怘揦嬛墝丒暘墝幚懺挷嵏寢壥偵偮偄偰曬崘偟傑偡丅
侾丄庴摦媔墝杊巭懳嶔尋廋夛偺奐嵜
庴摦媔墝杊巭懳嶔尋廋夛偵偼丄巗撪堸怘揦偺巤愝娗棟幰43柤偑嶲壛偟傑偟偨丅
丂幚懺挷嵏偼俈侽侽侽審偵懳偟偰峴偄丄寢壥俆侽侽侽審傪彮偟壓夞傞夞摎傪摼傑偟偨丅偦偺挷嵏偺嵺偵乽崱屻偍抦傜偣摍偺楢棈傪偟偰傕椙偄偐乿偲偄偆崁栚傪愝偗丄偦偙偱椆彸傪摼偨俇俁侽柤偵崱夞偺乽庴摦媔墝杊巭懳嶔尋廋夛乿偺埬撪傪弌偟傑偟偨丅侾俀俀柤偺曉怣拞丄尋廋夛嶲壛壜擻幰偑24柤丅嶲壛幰偑摉弶偺梊掕傛傝偁傑傝偵彮側偐偭偨偺偱丄媫绡奐嵜抧偺屗敤嬫偲嬤椬偺庒徏嬫偺彜揦奨偵僠儔僔傪帩嶲偟丄63尙偵屗暿朘栤偟傑偟偨丅
丂偦偺嵺偵丄揦曑愑擟幰偐傜乽尋廋夛偵弌偰偟傑偆偲揦偵扤傕偄側偔側偭偰偟傑偆偺偱弌傜傟側偄乿乽乮庴摦媔墝懳嶔傪乯壗偐偟側偔偰偼側傜側偄偲巚偆偗傟偳嬥慘揑偵擄偟偄乿乽彫偝偄揦偩偐傜嬛墝偟偨傜偍媞偑棃側偔側傞乿摍乆丄嬶懱揑側惗偺惡傪暦偔偙偲偑偱偒丄乽傕偭偲嵶偐偔丄椙偄曽岦偵岦偐偆偙偲偑偱偒傞傛偆偵峫偊偰偄偐側偗傟偽側傜側偄乿偲偄偆壽戣傪摼傑偟偨丅
俀丄巤愝撪嬛墝丒暘墝嫤椡億僗僞乕丄僠儔僔嶌惢攝晍
乽巤愝撪嬛墝丒暘墝億僗僞乕丄僠儔僔乿傪嶌惢偟丄彜岺夛媍強壛擖婇嬈俉侽侽侽売強偵丄夛媍強偺姧峴暔偲摨憲偟傑偟偨丅
丂偙傟偵偼巀斲椉榑偁傝傑偟偨偑側偐側偐偺斀嬁偱丄俉侽侽侽売強偺傎偐偵岞嫟巤愝丄堸怘揦俀侽侽侽売強偵傕攝傝傑偟偨丅
丂崱夞偺億僗僞乕傗僠儔僔偼丄乽巤愝撪偺嬛墝丒暘墝偵偛嫤椡傪乿偲偄偆傕偺偱丄堸怘揦梡偵嶌偭偨傕偺偱偼側偐偭偨偺偱丄堸怘揦偺曽偐傜偼乽傕偭偲僜僼僩側傕偺傪嶌偭偰傕傜偊側偄偐乿偲偄偆堄尒傕偁傝傑偟偨丅
俁丄堸怘揦嬛墝丒暘墝幚懺挷嵏寢壥偵偮偄偰
乮仸暥拞偺僌儔僼帒椏偼慡偰丄杒嬨廈巗曐寬暉巸嬊偺亀媔墝偵娭偡傞忬嫷挷嵏曬崘彂亁傛傝堷梡偟偰偄傑偡丅乯
丂杒嬨廈巗偺堸怘揦偵偍偗傞媔墝偵娭偡傞幚懺偵偮偄偰偺挷嵏寢壥偱偡丅
丂忬嫷挷嵏偼暆峀偄擭楊憌偑棙梡偡傞堸怘揦偱峴偄傑偟偨丅曽朄偼丄巗撪俆俉俉俈審偺堸怘揦偺愑擟幰偵懳偟偰傾儞働乕僩傪儊乕儖曋偱憲傝丄侾俋俉俇審丄33.俈亾偺夞摎偑偁傝傑偟偨丅崱夞俈侽侽侽審偵傾儞働乕僩傪弌偟偨偺偱偡偑丄栺侾俀侽侽審偑埗愭晄柧偱栠偭偰偒傑偟偨丅偐側傝捈嬤偺僨乕僞偩偭偨偺偱偡偑丄偦傟偩偗堸怘揦偺棳摦偺寖偟偝傪帵偟偰偄傑偡丅
俙丄寬峃憹恑朄偺廃抦忬嫷
丂寬峃憹恑朄偵偮偄偰乽棟夝偟偰偄傞乿俈.俈亾丄乽撪梕偼戝懱傢偐傞乿23.俁亾丄乽柤慜偼暦偄偨偙偲偑偁傞乿20.侾亾偱丄偙偺俁偮傪偁傢偣偰傕51.侾亾偱偡丅
丂帪婜揑偵偼寬峃憹恑朄巤峴屻俋儢寧偨偭偨崰偱偟偨偑丄47.俁亾偑寬峃憹恑朄傪抦傜側偄偲偄偆幚懺偑柧傜偐偵側傝傑偟偨丅
| 乮帒椏侾乯 | 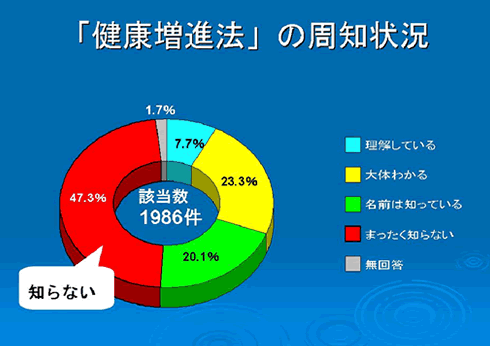 |
俛丄庴摦媔墝偺廃抦忬嫷
丂傑偨丄乽庴摦媔墝偲偄偆尵梩傪抦偭偰偄傑偡偐乿偲偄偆栤偄偵懳偟偰丄乽棟夝偟偰偄傞乿17.侽亾丄乽偩偄偨偄傢偐傞乿26.俇亾偱椉曽偁傢偣偰傕39.俇亾偱偟偨丅偙傟偵懳偟偰乽柤慜偼暦偄偨偙偲偑偁傞乿15.俈亾丄乽慡偔抦傜側偄乿38.俀亾偱丄愑擟幰偺敿悢埲忋偼庴摦媔墝偵懳偟偰擣幆偑晄懌偟偰偄傑偟偨丅
丂崱屻偼寬峃憹恑朄偍傛傃偦偺庯巪偺廃抦偑嵟戝偺壽戣偱偡丅
| 乮帒椏俀乯 | 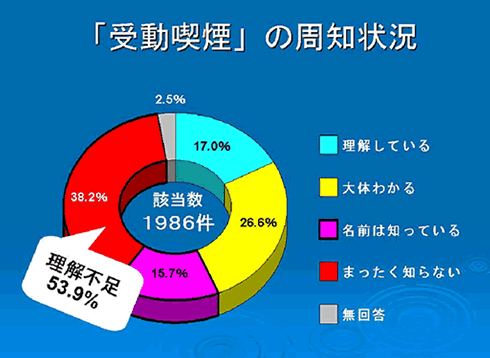 |
俠丄媔墝懳嶔偺幚巤忬嫷偲懳嶔偺幚懺
丂乽壗傜偐偺媔墝懳嶔傪峴偭偰偄傑偡偐乿偲尵偆栤偄偵懳偟丄媔墝懳嶔傪幚巤偟偰偄傞揦偼26.俋亾丄偙偺拞偱庴摦媔墝傪杊巭偡傞忋偱桳岠側懳嶔偑庢傜傟偰偄偨揦偼丄乽揦撪嬛墝乿俇.俇亾丄乽晹壆偲偟偰暘棧乿侾.俇亾丄乽僼儘傾偲偟偰暘棧乿侽.俈亾偺崌寁俉.俋亾偱慡懱偺侾妱偵傕懌傝傑偣傫丅
丂桳岠側懳嶔傪偟偰偄傞偲偄偆揦傕丄嬻娫傪巇愗偭偨偩偗丄応強傪巇愗偭偨偩偗丄嬛墝僞僀儉傪愝掕偟偨偩偗偲偄偆傛偆側晄廫暘側懳嶔偑懡偄傛偆偱偡丅
丂枹懳嶔揦偼丄儔乕儊儞丄拞壺丄從擏丄嫃庰壆偑旕忢偵懡偄偱偡丅
| 乮帒椏俁丒係乯 | |
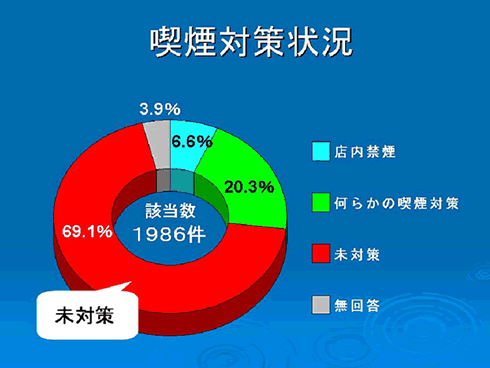 |
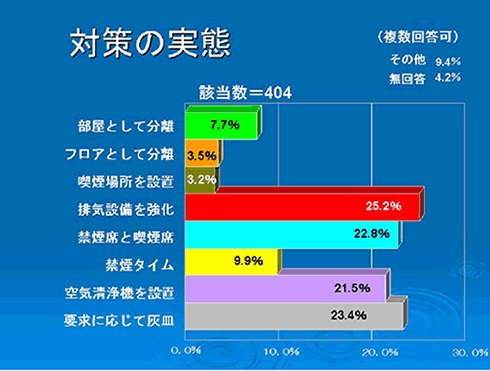 |
丂埲忋偺偙偲偐傜丄懡偔偺堸怘揦偵偍偄偰丄戝惃偺偍媞條偑庴摦媔墝偺旐奞傪庴偗偰偄傞偲偄偆幚懺偑柧傜偐偵側傝丄崱屻偼偍媞條偺傒側傜偢廬嬈堳傑偱娷傔偨庴摦媔墝偺杊巭偵攝椂偟側偑傜専摙傪恑傔偰偄偐側偗傟偽側傝傑偣傫丅
丂傑偨丄揦偵傛偭偰偼18丄19嵨偲偄偭偨枹惉擭偺廬嬈堳傕偍傝丄偙傟傜枹惉擭幰傕僞僶僐偺奞傪庴偗偰偄傞偲偄偭偨幚懺傕偁偒傜偐偵側傝丄偙傟偵懳偡傞懳嶔傪悇恑偟偰偄偔傋偒偩偲偄偆巜恓偑弌傑偟偨丅
俢丄揦撪嬛墝揦偺嬛墝奐巒帪婜偲偦偺棟桼
丂揦撪嬛墝揦侾俁俀審偺暘愅偲偟偰丄揦撪嬛墝偺奐巒帪婜偼丄偦偺25亾偑寬峃憹恑朄巤峴屻偱偟偨丅
丂嬛墝偵偟偨棟桼偲偟偰偼丄乽偍媞條偺寬峃乿乽壠懓楢傟偺偍媞偑懡偄乿偲偄偆偺偑偦傟偧傟28亾偱嵟傕懡偄偙偲偐傜丄寬峃憹恑朄偵傛偭偰揦曑偺嬛墝壔偑懀恑偝傟偰偄傞偙偲偑偆偐偑偊傑偡丅摿偵揦曑偺庬椶暿偺幚巤忬嫷偱偼丄枹惉擭幰偑棙梡偡傞僼傽僗僩僼乕僪揦偱偼38揦拞丄36.俉亾偑嬛墝壔偟偰39.俆亾偑壗傜偐偺暘墝懳嶔傪偟偰偍傝丄撍弌偟偰偄傑偟偨丅偦偺懠偲偟偰偼丄乽枴傪戝帠偵偟偰偄傞乿乽暤埻婥傪戝帠偵偟偰偄傞乿偲偄偆棟桼偑懡偄偱偡丅
| 乮帒椏俆丒俇乯 | |
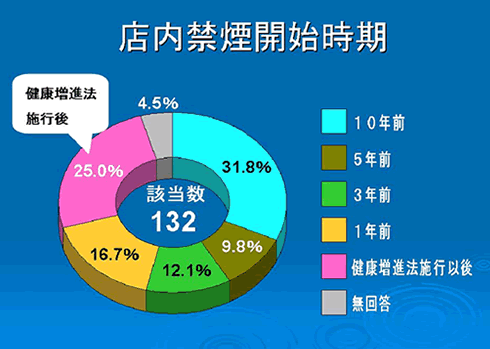 |
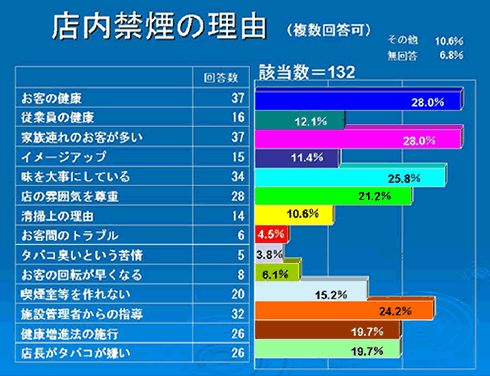 |
俤丄揦撪嬛墝偵懳偡傞偍媞偺斀墳
丂揦曑偺嬛墝壔傪寛掕偐偡傞偳偆偐偼攧忋偵懳偡傞晄埨偑旕忢偵戝偒偄偺偱偡偑丄嬛墝壔偺棃媞悢偲攧忋偵梌偊傞塭嬁偲偟偰偼丄乽棃媞悢偑憹偊偨乿侾.俆亾丄乽憹尭側偟乿29.俆亾丄乽尭偭偨乿12.侾亾偲偄偆寢壥偱偡丅
丂攧忋偼丄乽憹偊偨乿侾.俆亾丄乽憹尭側偟乿25.俉亾丄乽尭偭偨乿10.俇亾偱偟偨丅慡懱偺侾妱偑尭偭偨偲偄偆夞摎偱偡偑丄嬛墝揦偼侾俁俀審偲旕忢偵彮側偄悢偺拞偺侾妱偱偡偺偱丄崱屻僒儞僾儖悢傪憹傗偟偰偄偔偲乽憹偊偨乿偲偄偆妱崌偑憹偊偰偄偔偺偱偼側偄偐偲偄偆梊應傪帩偭偰偄傑偡丅
| 乮帒椏俈乯 |  |
俥丄揦撪暘墝揦偺暘墝奐巒帪婜偲偦偺棟桼
丂揦撪暘墝揦偼係侽係揦偁傝傑偟偨丅偦偺偆偪暘墝懳嶔奐巒帪婜偼13.侾亾偑寬峃憹恑朄巤峴屻偲偟偰偄傑偡丅
丂棟桼偼乽偍媞條偺寬峃乿35丒侾亾丄乽媔墝幒側偳傪嶌傟側偄乿20.俆亾丄乽廬嬈堳偺寬峃乿17.俉亾偲偄偆寢壥偱偡丅
| 乮帒椏俉丒俋乯 | |
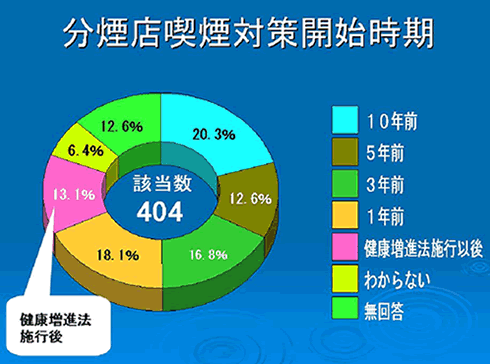 |
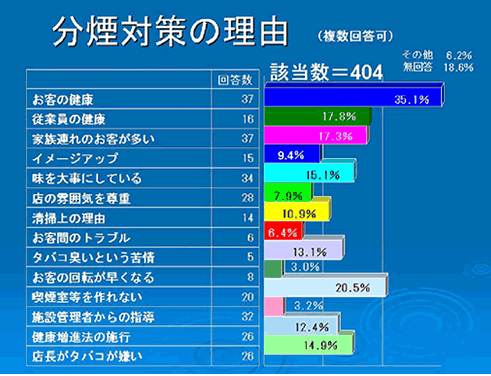 |
俧丄媔墝枹懳嶔揦偺棟桼
丂枹懳嶔揦偼侾俁俈俁揦偲堦斣懡偄偱偡偑丄枹懳嶔偺棟桼偼乽屄恖偺帺桼丒嫮惂偱偒側偄乿61.侽亾丄乽媔墝幰偑懡偄乿54.侽亾丄乽攧忋偺尭彮乿25.俀亾丄乽暤埻婥傪戝帠偵偟偰偄傞乿15.俈亾偺弴偱偡丅屄恖偺帺桼偱偁傝嫮惂偱偒側偄偲偄偆偺偼丄揦曑柺愊偺彫偝偄揦偑懡偄傛偆偱偡丅
| 乮帒椏10乯 |  |
俫丄揦撪暘墝揦偺媔墝懳嶔悇恑梊掕
丂暘墝揦偺崱屻偺懳嶔悇恑梊掕偼丄乽偁傞乿俇.係亾丄乽専摙偟偰傒偨偄乿37.侾亾偱丄椉曽崌傢偣偰43.俆亾偑峫偊偰偄傞忬嫷偱偡丅
丂枹懳嶔揦偱偼丄乽偁傞乿俀.俁亾乽専摙偟偰傒偨偄乿20.俁亾偱崌傢偣偰22.俇亾偼峫偊偰偄傞傛偆偱偡丅
| 乮帒椏11乯 | 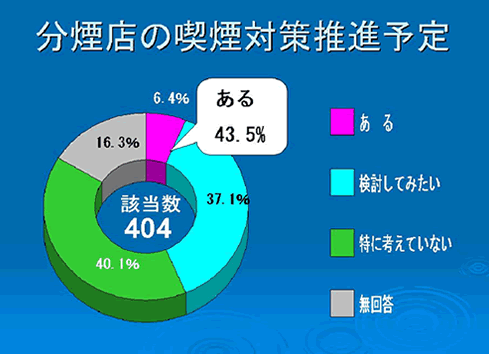 |
俬丄媔墝枹懳嶔揦偺媔墝懳嶔悇恑梊掕
丂枹懳嶔揦偵懳偟偰嬶懱揑側忣曬敪怣傪偡傞偙偲偱丄夵慞偱偒傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傑偡丅
| 乮帒椏12乯 | 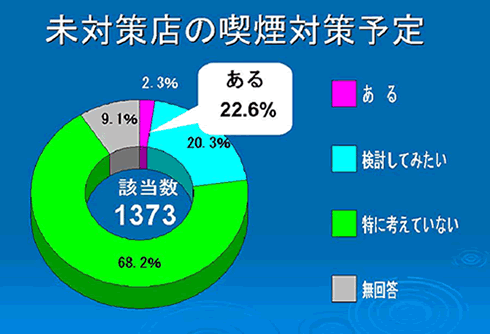 |
俰丄揦曑愑擟幰偑巗偵媮傔傞懳嶔
丂揦曑愑擟幰偑巗偵媮傔偰偄傞懳嶔偼丄乽億僗僞乕丒僠儔僔摍乿31.俁亾丄乽嬶懱揑側朄椷側偳偺惍旛乿26.侾亾丄乽揦奜偐傜媔墝懳嶔偑傢偐傞僗僥僢僇乕乿25.俉亾側偳偑偁傝傑偟偨丅峴惌偑幚巤偵岦偗偰専摙傪恑傔傞昁梫偑偁傝傑偡丅
| 乮帒椏13乯 | 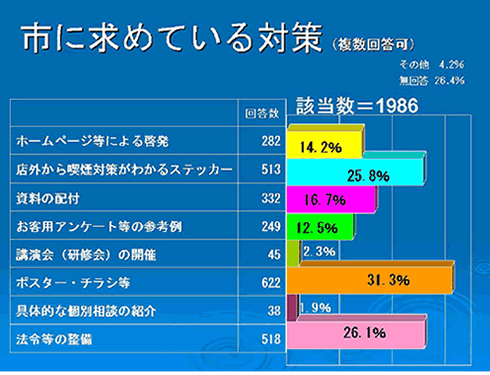 |
係丄挷嵏寢壥偺傑偲傔
嘆乽寬峃憹恑朄傪抦傜側偄乿乧47.俁亾
嘇乽庴摦媔墝枹懳嶔乿乧69.侾亾
嘊僼傽僗僩僼乕僪乧38揦拞丄36.俉亾偺14揦偑嬛墝丅39.俆亾偺15揦偑暘墝懳嶔傪偲偭偰偄傞丅
嘋僼傽儈儕乕儗僗僩儔儞乧32揦拞丄俋.係亾偺俁揦偑嬛墝丅68.俉亾偺22揦偑暘墝懳嶔傪偲偭偰偄傞丅揦撪嬛墝壔偵傛傞棃媞悢丄攧忋尭偼侾妱偺傒丅偙偺侾妱傪懡偄偲尒傞偐彮側偄偲尒傞偐偺寢榑偼傕偆彮偟帪娫偑妡偐傞偲巚偄傑偡丅
俆丄慡懱偺傑偲傔
侾丄寬峃憹恑朄偺偝傜側傞廃抦丄揦撪嬛墝揦偺攧忋尭彮偼侾妱偱偁傞偙偲傪娷傔偨庴摦媔墝杊巭懳嶔偺孾敪偺峀曬妶摦
俀丄庴摦媔墝懳嶔偵娭偡傞憡択憢岥側偳偺惍旛
俁丄愊嬌揑側庴摦媔墝懳嶔偵庢傝慻傫偱偄傞揦曑傪彠椼偡傞擣徹惂搙摍偺妋棫
係丄屭媞偺傒側傜偢丄廬嬈堳偺庴摦媔墝傪杊巭偡傞偨傔偵丄堸怘揦偺嬛墝壔偺悇恑
俆丄媔墝棪偦偺傕偺偺掅尭偵岦偗偰丄愊嬌揑側庢傝慻傒丄朄椷摍偺惍旛
仸偙偺崁偼丄杒嬨廈巗曐寬暉巸嬊曐寬堛椕晹寬峃悇恑壽庡嵏丒烴杮傦傝巕偝傫偺儗僋僠儍乕傪傑偲傔偨傕偺偱偡丅
乽堸怘揦偺暘墝懳嶔億働僢僩僽僢僋乿傪敪峴
 |
丂慡堸楢偱偼丄庴摦媔墝偺杊巭偺昁梫惈偲丄惓偟偄暘墝懳嶔偺峫偊曽傪夵傔偰慻崌堳偺奆偝傫偵棟夝丄擣幆偄偨偩偔偨傔偵丄乽堸怘揦偺暘墝懳嶔億働僢僩僽僢僋乿傪嶌惉偟丄慡崙偺慻崌堳偵攝晍偟丄暘墝懳嶔偺悇恑偵搘傔偰偄傑偡丅 |
