全 飲 連 デ ー タ フ ァ イ ル
ZENINREN DATA FILE
国民生活金融公庫「生活関連企業におけるIT活用状況」
導入状況、業種間に格差。ホームページの活用進む。
飲食業では70%に迫る。
平成12年度10月〜12月期の国民生活金融公庫が行った「生活関連企業の景気動向調査」の中で、生活関連企業におけるITの活用状況についても調査が実施されましたので、その結果をご紹介します。
コンピュータの導入状況
コンピュータを導入している生活関連企業は、23.6%と、四分の一程度となっています。「全国小企業動向調査(2000年6月)」(当公庫総合研究所)によれば、コンピュータを導入している小企業は46.3%となっており、生活関連企業の導入状況はあまり進んでいないことが分かります。
業種別では、半数以上で導入しているのが「ホテル・旅館業」と「映画館」の二業種で、「ホテル・旅館業」においては予約管理、フロント会計等パソコンによるフロント業務管理が進んでいること、「映画館」においてはパソコンによるチケット販売管理が進んでいることなどがその要因と考えられます。その一方で、業種柄コンピュータに対するニーズの小さい「公衆浴場」が5.9%となっており、コンピュータの導入状況は、業種間で格差がでています。
コンピュータの活用状況
もっとも多いのが、「インターネット」となっており、次いで「財務管理」、「顧客管理」が続いています。その一方で、「販売管理」、「仕入管理」、「企画・開発」等に活用している企業はまだ少ないようです。フェイストゥフェイスのサービス提供を主体とする生活関連企業においては、コンピュータの活用は、販売促進や固定客作りに重点が置かれる傾向にあると言えます。
しかし、個人消費が低迷する中では売上の大幅増加は望めず、採算性の向上を図るためには経費節減等の企業努力がこれまで以上に必要になってきています。サービス提供主体の生活関連企業においても、今後は、販売・仕入管理面にもコンピュータをこれまで以上に活用していくことが求められます。
「インターネット」に活用している企業を業種別にみますと、全業種平均44.4%に対して、「ホテル・旅館業」が61.7%と高くなっており、ホームページから宿泊予約ができるホテル・旅館が増加していることを反映しています。また、「顧客管理」については、全業種平均38.0%に対して、「クリーニング業」(63.3%)、「理容業」(63.1%)、「美容業」(57.9%)が他業種に比べて突出しており、固定客作りのため、パソコンによる顧客管理に活用している状況がうかがえます。
さらに「インターネット」に活用している企業がどのような目的で活用しているのかについてみてみますと、広告・宣伝を目的とする「ホームページ」の活用がもっとも多く、以下、「情報収集」、「電子メール」、「予約・販売受付」となっています。生活関連企業におけるインターネットの活用については、ホームページでお店のPRに活用するところが多く、特に「ホテル・旅館業」(77.1%)、「飲食業」(68.3%)においてホームページの活用が進んでいます。
この二業種においては、「宿ネット」、「ぐるなび」など専用の検索サイトが充実しており、これらのサイトに登録することによってPRに活用するところもあるようです。(田上 和彦)
外食産業市場動向調査
5月度概況
日本フードサービス協会では、毎月、業界の動向や変化を的確に示すデータの構築により、会員社の経営に役立つ情報提供及び、協会活動の一つとして、社会に対し、外食産業からの信頼性のある情報提供を目指し、外食産業市場動向調査を実施しています。この調査は、実態に即した精度の高い情報を得るため、全店データ(会員社本部から、新規店の売上高も含めた全店に関する基礎情報を把握)と既存店データ(会員社本部から、既存店に関する基本情報を把握)の二種の構成で、全国規模で行われています。集計方法及びデータ数値は、全店データ、既存店データともに回答事業社数をベースにした前年同月比を指標としています。また、業態に関しては通産省商業統計を参考に区分しています。
【全店ベース】
●トータルの売上は前年同月比102.3%
●客単価は下がるが客数が増加
平成13年5月度の外食市場動向について、新規の出店を含めた全店ベースでの売上は、全体で対前年同月比102.3%と前年を2.3ポイント上回った。
客単価は97.6%と前年を下回ったが、客数が104.8%と伸びたことが売上増に結びついている。各業態とも売上は前年を上回っているが、とくにファーストフードの和風や麺類、ファミリーレストランの中華と焼肉さらに居酒屋が2桁の売上増となり、この分野の規模を拡大している。反面、ファーストフードの洋風と持ち帰り米飯、ファミリーレストランの洋風、パブ・ビヤホールの分野が前年を下回る結果となった。
外食市場全体の店舗数は104.5%で前年に比べ4.5ポイント増加しており、出店意欲は依然旺盛である。とくにファミリーレストランの中華と、居酒屋は前年に比べ2割前後の増加となっている。
客数では、ファーストフードの麺類とファミリーレストランの焼肉が2割を超える大幅増と活況を呈している。
【既存店ベース】
●売上は前年同月比95.7%
●客数はFFの和風と麺類、喫茶の分野で前年を上回る
既存店ベースでの全体の売上は前年同月比で95.7%と前年を4.9ポイント下回る結果となった。
客数は97.5%、客単価は98.2%といずれも前年割れで推移した。客数減は昨年に比べ土曜日が1日少ないことやゴールデンウィーク中の天候不順の影響もある。客単価はファミリーレストラン等では下げ幅は僅かであるが、ファーストフードのなかの洋風、和風さらに麺類の分野で下げているのが目立つ。
ファーストフードの業態は、全体の売上は前年比94.9%、客数は98.4%、客単価は96.4%と前年を下回った。とくに洋風FFの売上は92.9%と大きく減少したが、前4月の低価格キャンペーンの残存効果があった和風FFでは、客数は前年を上回り、ほぼ前年並みの売上となっている。
ファミリーレストランの業態は、全体の売上は前年同月比96.2%、客数96.5%、客単価99.7%で推移した。
客単価は和風および中華FRで前年をアップし全体では僅かな下げとなっているが、客数が伸び悩んだ。
パブ・居酒屋の業態は、売上95.5%と前年を4.5ポイント下回った。客数は96.8%、客単価は98.6%であったが、居酒屋の分野では前年並みの客単価を維持している。
ディナーレストランの業態は、売上は98.4%であったが、客数99.3%、客単価99.1%と下げ幅は少なくなっている。
喫茶の業態は、客数は101.2%と前年を上回ったが、客単価が98.2%で、売上は99.4%と前年を僅かに下回った。
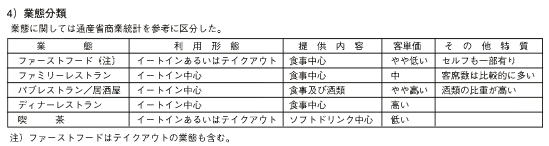
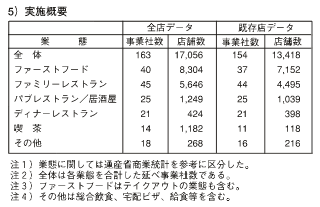
群抜く結婚披露宴の食べ残し 農水省が初めて調査
食品ロス統計調査
農林水産省は、平成12年度「食品ロス統計調査」の結果を発表しました。一般家庭および外食産業の消費段階と食品小売業、食品卸売業、食品製造業を対象に、食品の食べ残しや廃棄処分される食品ロスの実態を調べたもので、わが国では初めての調査です。
昨年、春の国会で成立した循環型社会形成推進基本法を軸とした7つの個別リサイクル法が制定され、そのうちの一つである「食品リサイクル法」が4月1日から施行され、今後の食品リサイクルの動向を占う指標となるもといえます。
パーティーも高い率。低い方は一般飲食店等
調査結果を単純に示すと一般家庭のロス率は7.7%、外食産業全体が5.1%、食品小売業1.1%、食品卸売業0.1%、食品製造業はほとんど0%となっています。
ただし、調査方法が異なるため、一概に比較することは困難です。一般家庭については、調査客体が実測、記帳に基づく自計申告調査とし、期間は昨年8月の1週間でしたが、廃棄はだいこんの皮の厚むきや、食肉の可食部分と判断されるべき脂身の除去などの過剰除去も含まれます。
一方、外食産業調査は、地方統計情報出張職員による実測調査とし、調査客体の販売メニューのうち5メニュー程度をサンプルとして調べました。期間は1日のうち3時間程度、または調査対象としたメニューが20食に達した時点で終了しました。
なお食品小売業、製造業などについては自計申告調査となっていますが、 廃棄については、家庭以外、外食産業を含めて、厨房内での可食食料の廃棄分や製造業の加工段階でのリンゴの皮、魚の骨、野菜くず、米ぬかなど不可食部分(歩留まり)は、調査客体の負担軽減等を考慮して調査の対象外としました。
従って、外食産業における廃棄は、「作り置き商品の廃棄」であり、実数はほとんど計上されていません。(調査客体数−家庭1千世帯、外食産業760事業所、食品小売業800事業所、食品卸売業720事業所、食品製造業1280事業所)。
外食産業全体の平均ロス率は5.1%ですが、業種・形態別・食品別のロス率ではかなり変化がみられます。とくに結婚披露宴とパーティーなどの宴会では飛び抜けて食べ残しのロス率が高くなっています。
総務省・日本標準産業分類に基づく外食産業分類の調査結果は、次のようになっています。
◎一般飲食店(喫茶店、大衆食堂、中華料理店、そば店等)=ロス率3.0%。「食べ残し」で多い食品類は、果実類の9.1%。次いでカタクリ粉などのでんぷん、豆腐などの豆類、風味調味料など。低い方ではサラダ油、オリーブ油などの油脂類、菓子類など。
◎旅館・その他の宿泊所等=ロス率7.2%。「食べ残し」で多い食品類は、魚介類の12.4%、果実類12.2%、干物、くん製品などの調理加工食品など。低い方では牛乳・チーズなどの乳製品、豆類などです。
◎結婚披露宴=ロス率23.9%。調査対策中、群を抜いて高いロス率。低いロス率の油脂類0.2%、卵類8.3%以外は、菓子類の30.6%、でんぷん29.2%など、20%台の高いロス率が軒並みになっています。
◎食堂・レストラン=ロス率3.6%。「食べ残し」で多い食品類は、果実類10.3%、でんぷん8.6%で、低い方では砂糖類1.3%、菓子類1.6%、肉類2.5%などです。
◎その他の一般飲食店=ロス率2.4%。「食べ残し」で多い食品類は、調味料類が7.8%、果実類7.4%が目立つ程度で、ほかは1.2%台で、低い方では油脂類が1.1%。またわずかですが、作り置きの廃棄で生鮮海藻類が0.1%ありました。
◎宴会=立食パーティーなどのロス率15.7%は結婚披露宴に次いで高く。「食べ残し」で多い食品類は、乳製品が30.5%、いも類27.3%、菓子類26.2%、調理加工食品19.6%。
低い方では、でんぷん7.3%のほかは2桁台で食べ残しになっています。
ロス率の高い東海、北海道、東北など
また外食産業全体について、地域別のロス率をみると、全国平均は5.1%ですが、ブロック別には東海の7.2%が最も高く、次いで北海道7.1%、東北5.6%、北陸5.4%、近畿5.0%、関東4.8%、中国・四国4.2%、九州・沖縄3.8%となっています。結婚披露宴と宴会のロス率によって大きく左右されていることがわかります。