 |
レジ袋有料化義務化に向けた 基本的な考え方(案) |
1. 見直しの目的
●「プラスチック資源循環戦略」(令和元年5月31日決定)では、資源・廃棄物制約、海洋ごみ対策、地球温暖化対策等の幅広い課題に対応しながら、プラスチックの資源循環を総合的に推進するための重点戦略の一つとして、リデュース等の徹底を位置づけました。その取組みの一環として、レジ袋有料化義務化(無料配布禁止等)を行い、消費者のライフスタイルに変革を促すこととしています。
●このため、プラスチック製レジ袋を含む容器包装の使用合理化に係る取組みを定める容器包装リサイクル法(以下「法」)の枠組みを基本としつつ、省令(※)の見直しを通じて、迅速かつ実効的なレジ袋有料化義務化を図ります。
※は小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化により、容器包装廃棄物の排出抑制の促進に関する判断基準となるべき事項を定める省令
2. 制度改正のイメージ
⑴レジ袋有料化の義務づけ
●プラスチック製のレジ袋については有料化の義務づけを行うこととする(プラスチック製レジ袋以外の容器包装(紙袋等)については、現行どおり複数の選択肢のうちいずれかの対応を義務づける)ことでよいか。
※現行体系…小売事業を行う際には、容器包装の使用の合理化が義務づけられており(法第7条の4第1項)、具体的手段として、①容器包装の有料化、②容器包装を利用しない場合のポイント還元、③マイバックの提供、④声がけの推進等、のいずれかを行うことが定められている(省令第2条第1項)。
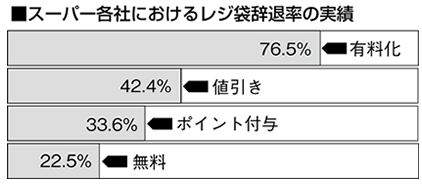 |
⑵対象となるレジ袋
●対象となるレジ袋は、①消費者が商品の購入に際し商品を持ち運ぶために用いる、②プラスチック製の袋とし(用途、素材による特定)、サッカー台のロール袋については、対象外とすることでよいか。
●生分解性プラスチック製の袋に関しては、相応の機能を有するものについては有料化の対象外とできるのではないか。
●他方、生分解性を有しないバイオプラスチックについては、海洋ごみの削減には寄与しない一方で、環境に配慮した素材であることを踏まえ、有料化の対象に含めるか否かについては要検討。
⑶有料化のあり方
●プラスチック製レジ袋の価値設定については、サイズ・用途や仕入れ主体・方法などにより、様々なケースがあると考えられることから、各事業者が自由に決定・選択できるものとするのが適切ではないか。
●また、レジ袋の収益の扱いについても、各事業者が自由に決定・選択できるとするのが適切ではないか。
⑷実効性の確保
●現行の法の枠組みを活用することで、実効性の確保に資することができるのではないか。
▶法に基づく容器包装多量利用事業者(年間50トン以上)による定期報告の活用。なお、フランチャイズチェーンの事業を行う者については、本部がその加盟事業者も含めて、取組状況を報告する。
▶法第7条の5に基づき、プラスチック製レジ袋の有料化等のあり方が不適切なときは、必要に応じて、指導及び助言を行うことができるとなっている。
●定期報告とは別に、各業界における自主行動計画によって取組状況のフォローアップの実施を推奨することでよいか。
⑸対象業種
●競争上の不公平を生じないよう、あらゆる業種においてレジ袋有料化等による削減努力がなされることが必要であるが、まずは、現行の法の枠組みを最大限活用することが適切ではないか。
●そのうえで、制度導入後の有料化等の実施状況を踏まえつつ、対象となる業種について必要な見直しを行い、追加を検討していくこととしてはどうか。
⑹小規模事業者等への配慮
●プラスチック製レジ袋の有料化については、事業者の規模にかかわらず一律に対象とすることが適切だが、小規模事業者等の有料化への円滑な移行に向けて、どのような配慮が考えられるか。
⑺実施時期
●実施にあたっては、システムの変更やレジ袋の使用変更等にかかる準備期間も十分に考慮しつつ、早ければ来年4月1日の施行をめざすことでよいか。
3. 国民理解の促進に向けて
●国民理解の促進に向け、以下のような取組みが考えられるのではないか。
▶レジ袋有料化にあたってのガイドラインの策定
▶各種メディアを通じた国民向け周知広報、各業界・各自治体への説明会等の実施
▶問合せ窓口の設置