| 専門的な知識、的確なアドバイスに応じられる指導者を育成 | ||
外食産業原産地表示アドバイザー育成セミナー
in 東京 |
||
 |
 |
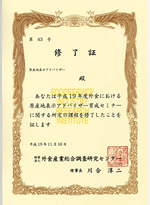 |
| 加川 正孝氏 | 船田 修平氏 | 修了証 |
去る11月16日、東京都千代田区の全国農業共済会館において、「外食産業原産地表示アドバイザー育成セミナーin東京」が開催されました。
昨今、食に対する安全性を揺るがす事件が増加し、それを懸念する消費者は、原産地表示を求める傾向にあります。そこで、原産地表示を普及・啓発すると共に、的確な指導やアドバイスに応じられる専門的な知識を持った「原産地表示アドバイザー」を育成する目的で、財団法人外食産業総合調査研究センターが今回のセミナーを主催。受講生はおよそ100名、5名の講師の講演に真剣な眼差しで耳を傾けました。
■宮城大学 食産業学部教授・池戸 重信氏
最近の外食産業の動向とそれに伴う消費者の意識に触れ、消費者は安全・健康面でのニーズが高まっているのに対し、供給サイドがそれに応えられていない状況の問題提起がなされました。そのうえで食の安全対策と表示制度に関する法的位置づけとして、食品安全基本法をはじめとする法や制度の説明が行われました。これらに基づいて積極的に安全を訴えることが、消費者の安心に繋がり、最も効果的な宣伝方法にもなると講演しました。
■(独)農林水産消費安全技術センターの新宅光一氏
「表示」に関する説明・注意事項などをJAS法やその関係法規と共に講演。生鮮食品、加工食品、無添加食品とそれぞれのカテゴリー別に具体的な表示法の指導を行いました。消費者の困惑や誤解を招く表記など誤った表記にならないよう、例を挙げながら注意を呼びかけました。
■農林水産省の船田修平氏
平成17年7月に策定された「外食における原産地表示ガイドライン」について、消費者がメニューを選ぶ上での重要な要素になると話し、自主的な指針でありながらも、広く推奨していく必要があると説明しました。ガイドラインの内容や、さらに事業者の実情に合った分かりやすい原産地表示ができるよう、メニューブックやサンプル、ホームページなど様々な例を紹介されました。
■堀井準一氏
実践事例の紹介では、自らが所属する㈱ゼンショク(焼肉店を中心に関西を拠点として全国的な店舗展開)が、BSE問題をきっかけに原産地表示を実施し、消費者の不安解消に取り組んだ経緯を紹介。情報提供こそがお客様との信頼関係を築く重要な取り組みであり、さらには生産者からお客様までの信頼関係作りになると訴えました。実施後のお客様の声を大切にし、自社分析を重ねることで、今後はさらに見やすくて分かりやすい原産地表示のシステム作りに取り組む姿勢の重要性を示しました。
■群馬県飲食業生活衛生同業組合の副理事長兼専務理事・加川正孝氏
自らが経営する蕎麦店(忠治庵)での原産地表示の実践経験を元に講演。加川氏は、飲食業界でこれまで最重要とされていた「衛生・清潔」だけでは消費者は満足しないと考え、更なるサービスとして原産地表示を積極的に導入し、情報公開に努めてきた経緯を紹介しました。
原産地表示の実施に先立ち、仕入れ品目や仕入先の全調査を行った際に、「お客様に提供する食材の情報を事業主自らが熟知する必要性と、その責任を痛感。調べることで余分なコストダウンにも成功し、経営面でもメリットがあった。今まで知らなかった食材の特徴を知ることもできたので、素材の情報に基づいて職人の技術を駆使し、食材を最大限に生かすことができる」と消費者だけでなく、事業主にとっても画期的な取り組みであると呼びかけました。
最後に、組合や地域など集団で取り組んでいくことがお客様に対して均一なサービスの提供に繋がると話し、その必要性を訴え「集団での取り組みには核が必要です。飲食店は業態も規模もそれぞれ異なり難しい面も多々ありますが、中心になって指導していける人達が必要なのです。皆さんが是非その核となり、引っ張っていってください」と、受講した100名の新しいアドバイザーにエールを送り、幕を閉じました。