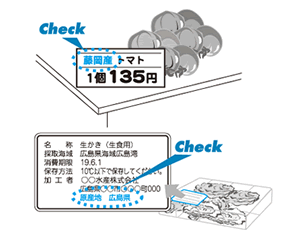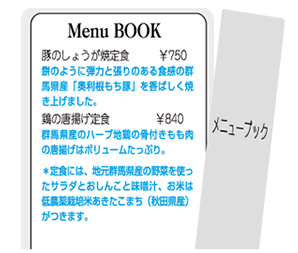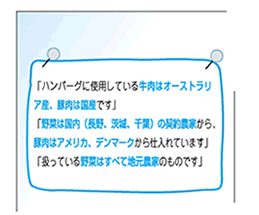●原産地表示ガイドブックを作成
全国飲食業生活衛生同業組合連合会では、平成18年度の生衛振興推進事業として、飲食店の原産地表示への取り組みを奨励しています。今回、組合員各店が原産地表示に取り組むうえで、重要なポイントをまとめました。
●原産地表示は消費者に浸透し支持されています。
BSE問題や食品の偽装表示事件、輸入農産物からの基準を超える残留農薬の検出などにより、食の安全・安心が脅かされ、消費者の食に対する関心が急速に高まりました。そのことにより「食品の表示」が従来にも増して重視されるようになり、スーパーなどの小売店ではすべての生鮮食品や加工食品に原産地や原産国の表示が義務付けられました。
消費者は商品を選択する際にここをチェックしています。今や表示があるものが普通で、表示のない商品を手にしたときはあなたもその商品を買うことを躊躇してしまいませんか?
●「外食における原産地表示のガイドライン」って?
今や外食は子どもから高齢者まで幅広い年齢層の人々に利用されています。外食が身近な食の場として安心して利用できるように、メニューにも原産地表示を要望する声が大きくなってきました。そのために農林水産省では、外食事業者が原産地表示を行うための指針「外食における原産地表示のガイドライン」を策定しました。
●対象となる事業者は? やらないと処罰?
「外食における原産地表示のガイドライン」は業種、業態や事業規模の大小にかかわりなく、すべての外食事業者を対象としています。ですが法的な拘束力はありません。なぜかと言うと、外食のメニューはさまざまな食材を使用していることが多く、同じ食材でも複数の産地のものを使っていたり、メニューの入れ換えが頻繁であったり、気候や季節でも産地が頻繁に変わります。また料理はその場で消費されますので、事後的な検証が難しいことなどから法的に義務づけることは困難なためです。
●お客様に安心をアピールするだけでなく
原産地表示を実施することは難しそうだし手間がかかり負担になりそう…。しかし、原産地表示をはじめる外食企業が徐々に増えてきているのは事実です。それは食の安全を求める消費者の信頼獲得のためであることはもちろんですが、原産地表示を行うことで、従業員の食の安全に対するモチベーションの向上にも一役買っているのです。
●まずは、できそうなところから。
あまり難しく考えず、まずは実施できそうな方法で手がけてみてはいかがでしょうか。 例えば、その日に使用する肉や野菜など素材の産地を、ボードや大きな用紙に「本日の素材」と題して書き出す。
「ハンバーグに使用している牛肉はオーストラリア産、豚肉は国産です」「野菜は国内(長野、茨城、千葉)の契約農家から、豚肉はアメリカ、デンマークから仕入れています」
原産地表示、できそう?
●すべてのメニューに表示しなくてはいけないの?
お店で使っているあらゆる材料や調味料に対し原産地を表示しなければならないわけではありません。
ガイドラインでは「1.メニューの主たる原材料、2.メニュー名に用いられている原材料、3.こだわりの原材料について、原産地を表示する」となっています。また、「4.お店の売れ筋メニューや定番メニューなどの「主要なメニュー」については、メインの原材料以外の原材料についても表示する」とされています。
1.メニューの主たる原材料
例:「しゃぶしゃぶ」の場合
【肉:上州牛】を表記
*主たる原材料=メニュー構成を決定する原材料のこと。
2.メニュー名に用いられている原材料
例:「厚切り豚のしょうが焼き」の場合
【豚肉ロース:鹿児島県産】を表記
3.こだわりの原材料
例:【福島県産・無農薬栽培米を使っています。】
*こだわりの原材料=品種、 栽培方法や産地等にこだわって 調達している原材料のこと。
4.主要なメニュー(売れ筋・定番メニュー)
例:親子丼の場合
【鶏肉:名古屋コーチン(愛知県産)、 卵:群馬県産、米:富山県産】を表記
●産地って、具体的にどのように表示すればいいの?
国産品の場合は「国産」、輸入品の場合は「原産国名」を表示します。そのほかにも一般に知られている地名を表示してもかまいません。
○国産の場合
都道府県名〈群馬県・北海道・京都府・山口県〉 地方名〈関東地方・東北地方・東海地方〉 地域名〈庄内・阿蘇〉 旧国名〈薩摩・近江・因幡〉
海域名〈銚子沖・日向灘〉 湖名〈宍道湖・十三湖〉 島名〈淡路島・佐渡ケ島〉
○外国産の場合
州名・省名〈フロリダ州・福建省〉 地域・都市名〈パルマ地域〉 湖名〈B国カスピ海〉 島名〈タスマニア島・ハワイ島〉 海域名〈A国地中海〉
●メニューブックに書かないとだめ?
原産地表示の方法や表示する場所は、お店の実情に合わせたものでOK。お客様にわかりやすく正しい情報を提供しましょう。
具体的な方法としては、メニューブックに表示する他にも、店内の目立つところにボードを置いたり、用紙を壁に貼っても良いでしょう。メニューサンプルを入口などにおいてある場合、一緒に表示するのも1つの方法です。
メニューブック
ボード
用紙を壁に貼る
メニューサンプル
●いろいろなことをアピールし差別化を図ることも
例えば、お店で意識的に地産地消を取り組んでいたり、農家と契約し栽培方法などにこだわっているなら、表示方法を工夫してどんどんアピールしましょう。
例:「野菜は地元嬬恋の契約農家の低農薬・有機栽培野菜のみを使用しています」
では、お店で実際にやってみましょう!
●担当者を決めましょう。
担当者を決めるときには、仕入業務に関わるスタッフも加えましょう。また、食材の仕入れ先業者へ原産地情報の提供の協力をお願いしておくことも重要です。
●曖昧な表示や誤認させるような表示は×
注意しておきたいのは、曖昧な表示や誤認させるような表示はしないこと。逆にお客様の不信感を募らせます。そのためにも仕入先から確かな産地情報を入手し、扱う食材についての情報をきちんと把握することが重要です。
●最初から頑張らないで、お店にあった方法を見つけましょう。
それぞれのお店にあった表示方法がきっとあると思います。まずやってみて原産地表示に対するお客様の反応をチェックしながら、お店に無理のない範囲で原産地表示を進めていきましょう。
●ステップアップ
原産地表示と併せて栄養成分表示やアレルギー表示も行ってみては? ここまでくればライバル店に大きな差をつけることができるでしょう。 原産地表示の詳細については、
農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/gaisyoku/)をご覧ください。 |